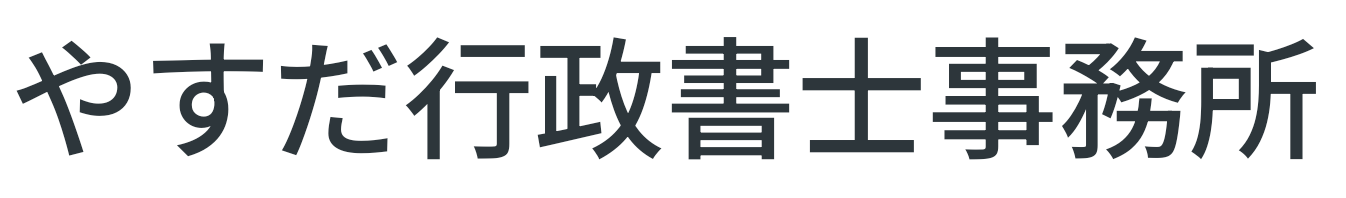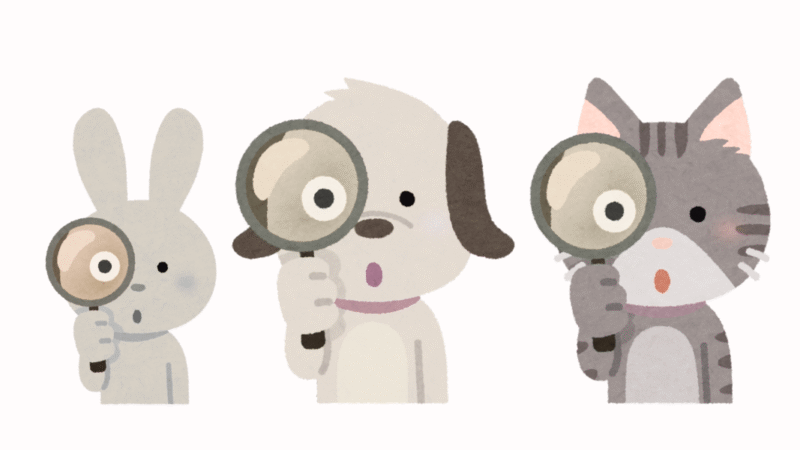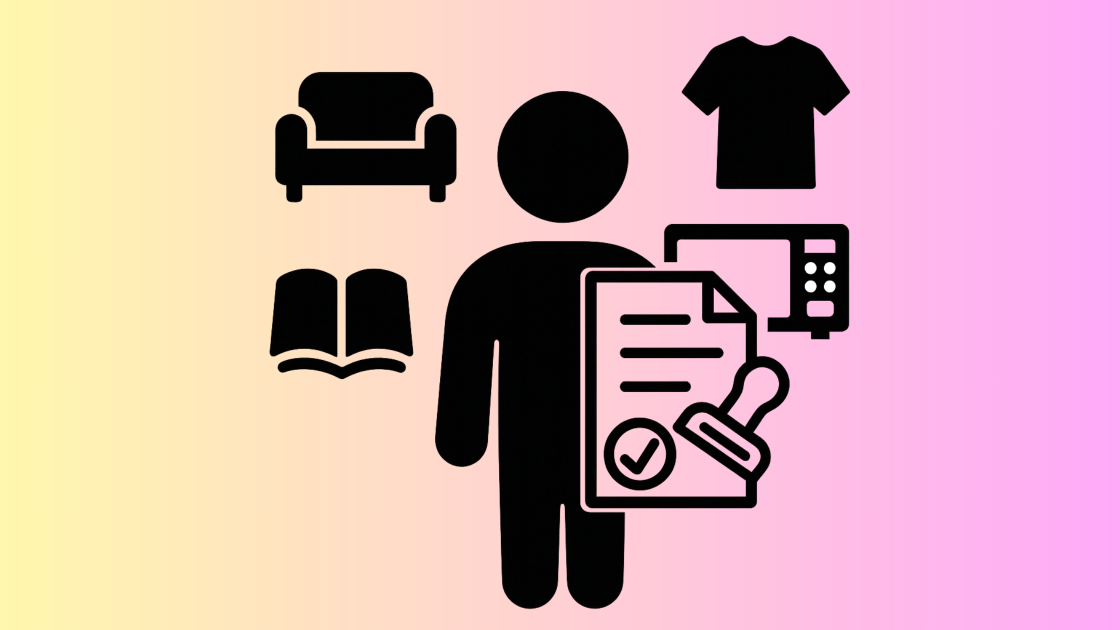
【ハンドメイド作家さん必見】中古材料を使うなら「古物営業許可」が必要って知ってた?
ハンドメイド業界では材料の調達方法や作品の販売方法が多様化しているにもかかわらず、法規制・法的リスクについては意外と知られていない/気にしていないのが現状です。
特に、中古の材料を使って作品を作っているなら要注意。「古物営業許可」が必要になるケースがあるんです。
この記事では、ハンドメイド作家が誤解しがちな古物営業許可の必要性について、具体例も交えて解説します。
なぜ古物営業許可が必要なの?
盗品の流通防止と速やかな発見を目的として「古物営業法」という法律が作られています。
中古品は、盗品が市場に紛れ込むリスクがあります。そのため、古物営業許可を取得した人だけが特別に中古品の売買ができる仕組みになっています。
この古物営業法に基づくルールでは、「中古品を仕入れ、加工や修理をして販売する行為」も古物営業に該当します。
たとえ大幅に加工して元の形が変わったとしても、材料が中古品である限り法的には『古物』の扱いとなります。
どういうときに必要?具体例から
次の2つの条件両方を満たす場合は、古物営業許可が必要です。
- 中古の材料を仕入れる
- その材料で制作した作品を販売する
古物営業許可が必要なとき(例)
- 中古の材料を使ってハンドメイド作品を作り、それをメルカリ、Creema、Minne、ラクマなどで販売する
- フリマアプリ(メルカリ、ラクマ)で購入した材料を使ってハンドメイド作品を作り、販売する
- 古着をリメイクして作ったバッグをフリーマーケットで売る
- 中古のパーツを使ってアクセサリーを製作し、ハンドメイドフェスティバルで売る
古物営業許可が不要なとき(例)
- 新品の材料のみを使用してハンドメイド作品を作り販売する場合
- 中古材料を使って作品を作るが、販売はしない場合(自分で使用する)
どうやって取得する?
古物営業許可の取得には、各都道府県公安委員会への申請が必要です。
手数料は通常19,000円程度がかかります。継続的にハンドメイド販売を行う予定であれば、適切に許可を取得されることをお勧めします。
申請は行政書士が代行することも可能です。行政書士費用は50,000円程度かかることが多いようですが、書類作成の手間や不備のリスクを心配することなく、スムーズに手続きを進めることができるので便利です。
取らないとどうなる?
許可が必要なのに取得せずに営業を続けていると、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金など)が科される場合があります。
古物営業許可なく営業を続けると、警察から行政指導や営業停止命令を受ける可能性があります。一度でも法的措置を受けると、信頼を失い、将来的にハンドメイド作家としての活動が難しくなることも考えられます。
もし、これまで許可なく営業していたことに気づいた場合は、速やかに許可取得の手続きを進めることが重要です。 その際、過去の状況について公安委員会への説明が必要になるケースもありますが、行政書士はそのサポートもできます。
まとめ
中古材料の活用はハンドメイドに役立ちますが、古物営業許可を取得しないまま作品作りを続けることは大きなリスクになります。
法的リスクを避けるためにも古物営業許可は早めに取得しておくことをお勧めします。安心してハンドメイド活動を続けるために、ぜひこの機会に確認してみてください。
当事務所でも古物営業許可の取得代行を承っております。相談だけでもOKですので、お気軽にご相談ください。