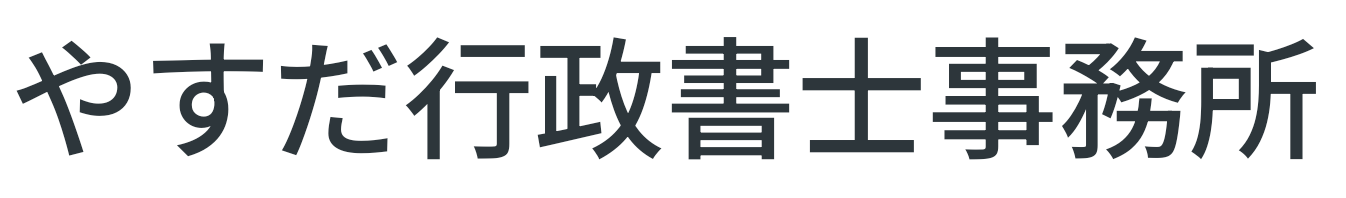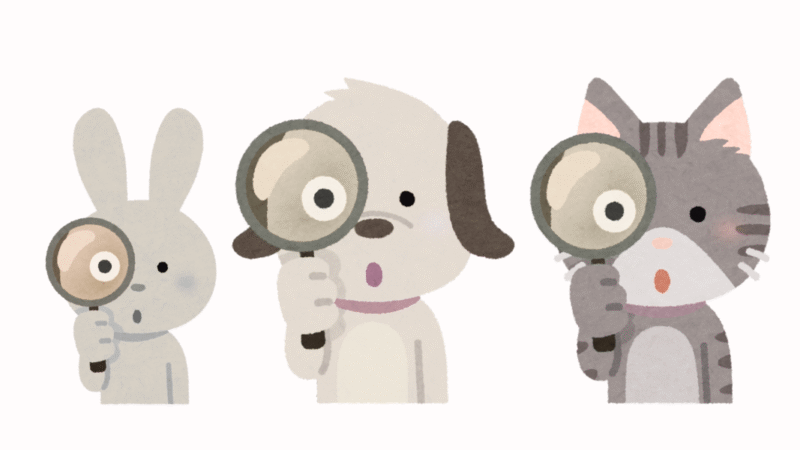2025年度(令和7年度)兵庫県の食品衛生監視指導計画
各都道府県では、食品衛生法第24条に基づき「食品衛生監視指導計画」を毎年策定する必要があります。
ここでは、兵庫県の2025年度(令和7年度)の食品衛生監視指導計画を見てみます。
県内の地域特性を踏まえ、広域的な食品流通に対応できる監視体制の整備と、重点項目に基づく指導を行っている点が特徴です。
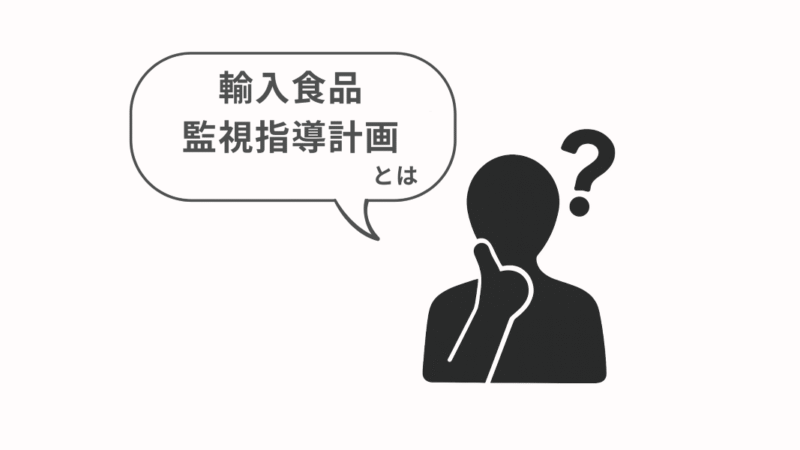
対象地域と連携体制
本計画の対象地域は兵庫県内全域ですが、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の5市は保健所設置市のため除外されています。
これら5市はそれぞれ独自に監視指導計画を策定しており、県とは「食の安全安心行政(県市)連絡会議」などを通じて連携しています。
監視指導の実施体制としては、次の機関が連携して役割分担を担っています。
- 健康福祉事務所(保健所)
- 県立健康科学研究所
- 食肉衛生検査センター
また、農林水産部局とも連携し、生産段階における食品安全規制にも取り組んでいます。
重点監視指導項目
兵庫県の計画では、以下の項目を重点的に監視・指導しています。
- 危害発生頻度の高い業種
- 健康被害発生時の影響が大きい大規模施設
- 広域流通食品の製造施設
特に、広域流通食品の製造・販売事業者については、
- 食品の入出荷情報の管理状況
- 期限切れ原材料の不適切な使用の有無
などを重点的に確認し、食品衛生管理体制の適正化を図っています。
食中毒対策とHACCPの推進
重点的に監視している施設や業種に対しては、実際にどのようなリスク対策を行っているのかも重要です。
兵庫県では、食中毒防止と衛生管理(HACCP)の定着に特に力を入れています。
食中毒対策
- ノロウイルスやカンピロバクターによる食中毒が多発しているため、季節に応じた予防対策を徹底
- ふぐ取扱施設に対する一斉監視も毎年実施
HACCPの推進
- 改正食品衛生法に基づくHACCPに沿った衛生管理の制度化への対応として、特に小規模事業者への導入支援を重視
- 県独自の「兵庫県食品衛生管理プログラム(県版HACCP)」認定制度を推進
リスクコミュニケーション
さらに兵庫県では、こうした事業者への衛生管理支援と並行して、県民との情報共有や意見交換にも力を入れています。
安全・安心な食品を提供するためには、行政・事業者・消費者が連携して理解を深めることが重要とされています。
兵庫県では、県民との情報・意見交換(リスクコミュニケーション)を重視しています。
- ホームページやSNSでの情報発信
- 意見交換会の開催
- 「出前講座」による知識普及
などを通じて、県民・事業者と行政が相互に理解を深める取り組みを行っています。
まとめ
兵庫県は、県内の広域流通食品の安全確保を重視した監視体制を整え、危害発生リスクの高い施設や事業者を重点的に監視しています。
また、小規模事業者へのHACCP導入支援や、県独自の認定制度といった取り組みを進めるとともに、県民とのリスクコミュニケーションにも力を入れている点が特徴です。