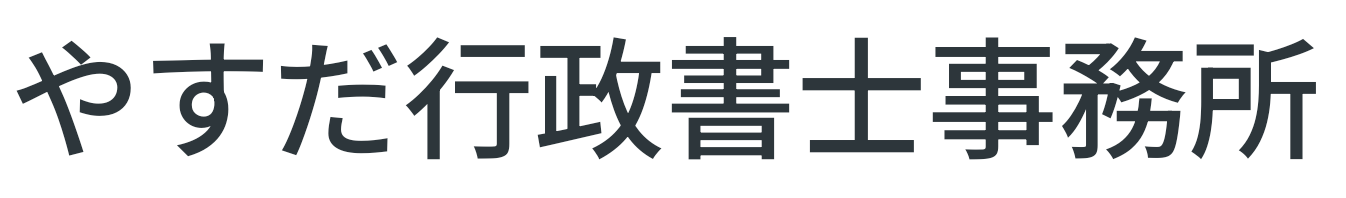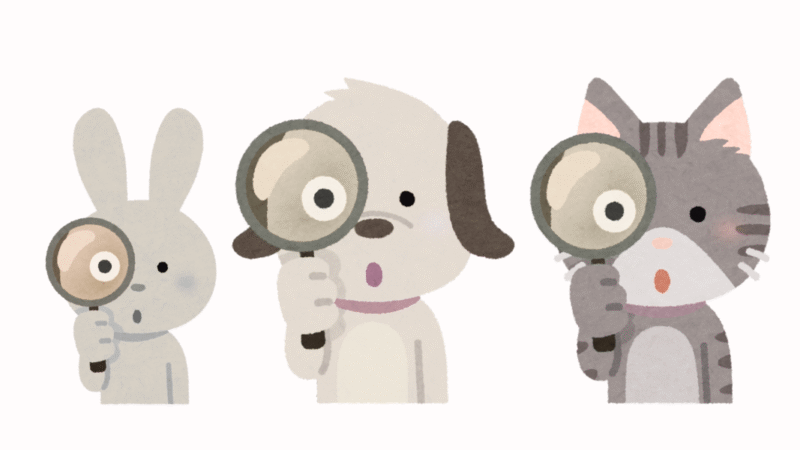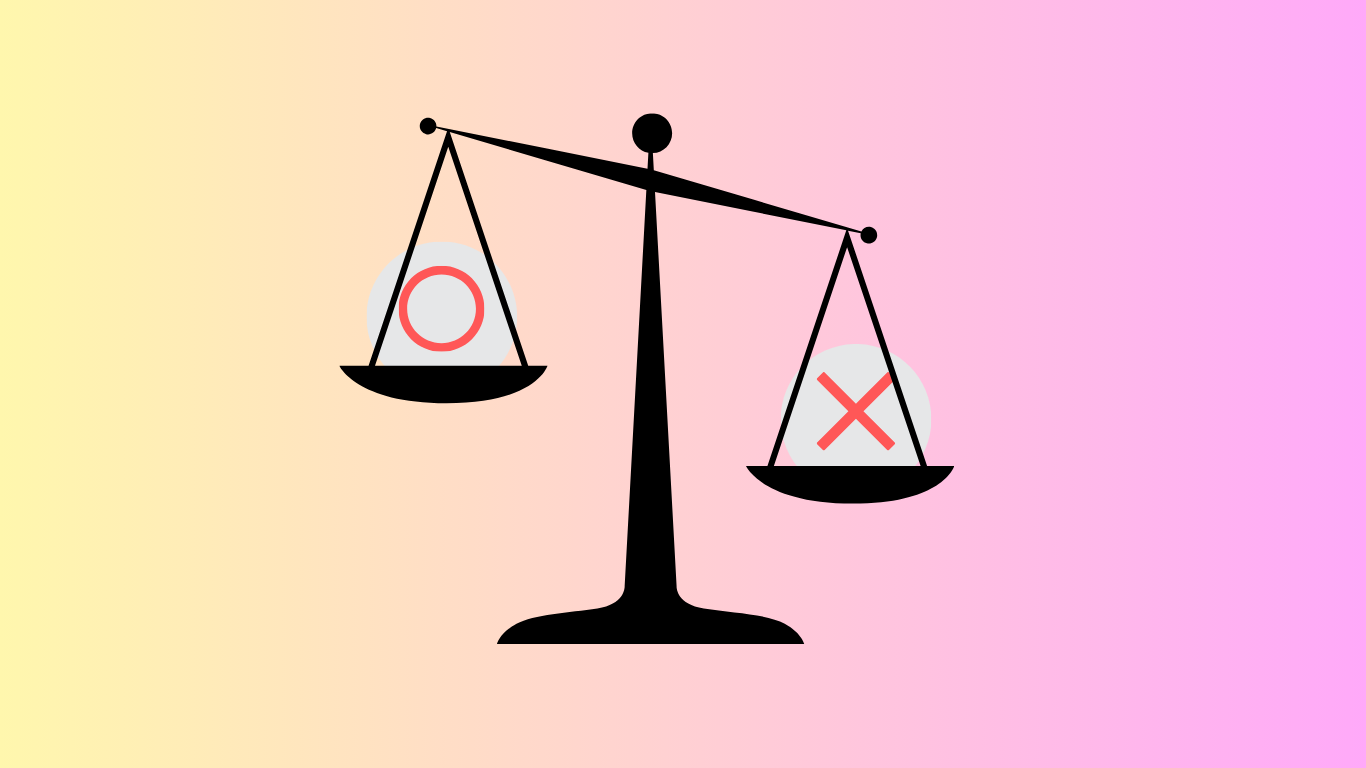
許可を取っても稼げない?! 建設業許可取得のメリットとデメリット
「建設業許可を取得すると稼げそう!」と考えている方は多いと思いますが、実際に許可を取るべきかどうかは、今後どんな案件を受けたいか、事業をどう広げたいかによって大きく変わってきます。
ここでは、建設業許可取得のメリットとデメリットを整理します。
建設業許可取得のメリット
よく言われるのは、「大型工事を受注できる」ことと「信用力UP」によって売上増加のチャンスが広がる、という点です。
メリット1:大型工事が受注できるように
建設業許可をもっていると税込500万円以上の工事を請け負うことができます(建築一式工事を除く)。
請け負える金額が大きくなるので、「より売上を上げていきたい」「大きな案件にチャレンジしたい」という方にとっては間違いなくメリットになるといえるでしょう。
| 工事の種類 | 許可が不要な工事 | 許可が必要な工事 |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 請負金額500万円未満 | 請負金額500万円以上 |
| 建築一式工事 | ①請負金額1500円未満 または ②延べ面積150㎡未満の木造住宅 | 左記を超える場合 |
※金額は「税込み」なので注意が必要です。すでに数百万円規模の案件を受けているなら、そろそろ検討のタイミングかもしれません。
メリット2:信頼性UP
建設業許可を取得するためには一定の要件や財産的基礎が求められます。
そのため、「許可を持っている」=「しっかりとした会社」と評価されやすく、取引先や金融機関からの信頼も高まり、ビジネスチャンスは広がります。
建設業許可取得のデメリット
「許可=メリットだらけ」と思いがちですが、デメリットもあります。
デメリット1:費用がかかる
まず大きなデメリットのひとつは、許可の取得や更新にコストがかかることです。
-1024x698.png)
コストの中でも特に大きなものは許可の取得にかかる手数料です。具体的な金額は申請先によって異なりますが、例えば兵庫県に申請する場合は次のとおりです。
新たに一般建設業の許可を取得する場合、9万円が手数料としてかかります(黄色マーカー部分)。
一旦取得した後も、更新(5年ごと)のたびに5万円が発生します(ピンクマーカー部分)。
デメリット2:手間が増える
許可取得後は、さまざまな報告・届出義務が発生します。
- 毎年決算終了後に行政への決算報告(※税務署に報告しているものとは別で、行政側に報告するものになります)
- 役員や営業所技術者などの変更時の届出
こうした事務的な手間も、許可を取る前にしっかりと把握しておきましょう。
デメリット3:情報が公開される
建設業許可を取得するために提出した資料は行政機関(兵庫県なら土木事務所)で誰でも閲覧できる状態になります。
提出書類の中には財務諸表も含まれているため、「財務内容を外部に知られたくない」と感じる方にとっては、デメリットとなり得ます。
「そんなもの誰が見に来るの…?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、閲覧可能日の土木事務所はかなり混雑しています。
デメリット4:許可を取っても、すぐに大型案件が受注できるとは限らない
許可を取得したからといって、必ずしもすぐに大きな案件が受注できるとは限りません。
将来的な事業計画や取引先のニーズをふまえて、「投資に見合うのか?」をしっかり検討することが大切です。
まとめ
建設業許可の取得は、規模の大きな工事を受注していきたい方には強い味方になりますが、小規模工事しか予定していない方には、コストや手間だけが負担になる可能性もあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ◎大型工事が受注可能に ◎信用力UP | ×費用がかかる ×手間が増える ×情報が公開される ×大型案件が来るとは限らない |
取得したものの、「申請後の更新や決算報告などが面倒だ」という声も少なくありません。
迷ったときはぜひ一度ご相談ください。一人一人の状況に合わせてベストな選択を一緒に考えましょう。