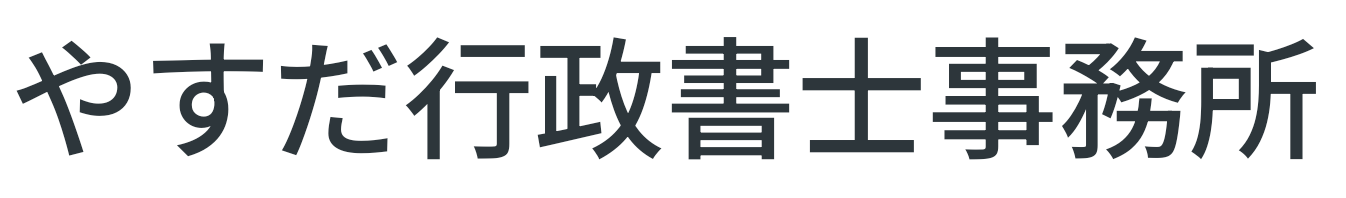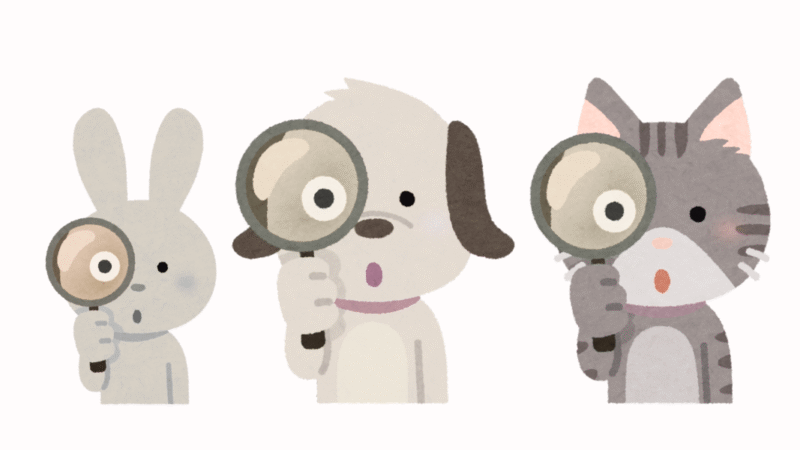【2025年12月改正】3歳未満向けおもちゃの「PSCマーク」規制|安全性確認と検査の進め方を徹底解説
2025年12月25日から、子ども用おもちゃに対する安全規制が大きく変わります。
これまでは事業者の「自主判断」で販売できていた製品も、今後は「法律で定められた技術基準に適合していることを確認し、PSCマークを表示しなければ販売できない」仕組みになります。
この記事では、製造・輸入事業者が必ず知っておくべき安全性確認の具体的な手順を分かりやすく解説します。

安全性確認の全体像(3つの義務)
まずは法律に則って販売するために必要な大きな流れを3ステップで把握しましょう。
1) 商品を企画・設計
まずは企画段階で「技術基準」に適合するよう設計します。
※「技術基準」の中身については後ほど解説します。
2) 製造・輸入のたびに検査(自主検査)
商品企画時だけでなく、製品を作るたび(輸入するたび)に検査を行い、その記録を作成・保管する必要があります。
「自主検査」と呼ばれますが、「任意」ではなく「義務」です。
3) 表示義務の遵守
検査に合格した製品にのみ、以下の情報を表示して販売することができます。
- PSCマーク
- 注意書き(警告表示)
- 届出事業者名
- 対象年齢
そもそも「技術基準」とは何か?
安全性を確認すると言っても、自分勝手な方法では認められません。「技術基準」という明確なルールに従う必要があります。
実質的には「国際規格」や「STマーク」のこと
法律上は小難しく書かれていますが、実務上は以下の国際的なおもちゃの製品規格が「技術基準」として扱われます。
- ISO 8124(国際標準化機構)
- EN 71(欧州規格)
- ASTM F963(米国規格)
- STマーク(日本玩具協会基準)
法律上は「これら以外の方法でも、合理的ならOK」とされていますが、それを証明するには高度な技術的知識が必要です。
そのため、多くの事業者はこれらの国際規格に基づいた検査を選択することになります。
具体的な検査の進め方(4ステップ)
では、実際にどうやって「規格に適合しているか」を確認するのでしょうか?
流れは以下のとおりです。
Step1: 検査機関を選ぶ
- どの規格(ISO,ASTMなど)で検査するかを決め、対応可能な試験機関を探します。
Step2: 製品を送る
- 製造者(ハンドメイド作家・メーカーなど)がサンプルを試験機関に送付します。
Step3: 検査を受ける
- 試験機関が規格に従って検査を実施します。例えば:
- 誤飲防止サイズ
- 強度
- 燃焼テスト
- 有害物質の有無 など
規格ごとに検査項目は異なります。
ISO 8124 と ASTM F963-23、STマークの内容は必ずしも同一ではありません。
Step4: 適合・不適合の結果を受領
結果の詳細は 試験報告書(Test Report) で確認します。
- 適合(合格)の場合は販売へ進みます。
- 不適合(不合格)の場合は改良して再試験するか、撤退を検討する必要があります。
- 試験報告書(Test Report)
「どの項目で不合格だったか」「どんな数値が出たか」という結果が書かれたもの。これだけでは「どう直せばいいか」までは分かりにくいことがあります。 - 基準書(規格書)
「小さい部品は〇〇mm以下はNG」「この塗料は使えない」といったルールそのものが書かれた設計図のような本です。
不適合だったらどうする?
もし検査に落ちたときは、以下の手順で原因を突き止めます。
- 適用規格を確認する
試験報告書を見て、どの条項に引っかかったかを確認します。(例:ISO 8124-1 小部品テスト) - 基準書の該当ページを確認
基準書のその条文を読み、「どのような試験方法で、何が基準なのか」を正確に把握します。 - 実物と照合・改善する
- 「部品が専用シリンダーを通り抜けてしまった」→ 誤飲リスクあり。部品を大きくしよう。
- 「燃焼速度が基準を超えた」→ 燃えやすい素材だ。材料を変更しよう。 など
このように、試験報告書(Test Report)を基準書(ルールブック)と照らし合わせることで、初めて具体的な改善策が見えてくるのです。
まとめ
基準書(規格書)は、メーカーや個人で購入することも可能ですが、1冊数万円することも珍しくありません。
「自分で購入して読み込む」か、「基準書を所持している専門家のサポートを受ける」か、ご自身の事業規模に合わせて検討が必要です
- 事業届出の開始: 2025年9月25日〜
- 規制の完全施行: 2025年12月25日〜
規制開始直前は検査機関や窓口が混み合うことが予想されます。早めに基準書の確認や検査手順の把握を進めていきましょう。
当事務所では、事業届の作成から、製品の検査・基準確認のサポートまでトータルで行っています。
「何から手をつければいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。